花コラム
花コラム 第10回:あじさいを咲かそう あじさいを根づかそう
2018.6.1 第10回:あじさいを咲かそう あじさいを根づかそう
梅雨時は、降り続く雨に気分は沈んでしまいがちです。そんな折でも、紫陽花(あじさい)を見かければ、フッと気持ちが明るくなります。紫陽花は、雨に映える花の代表と言えるでしょう。
紫、青、紅,白など様々な色の花を小鞠のように咲かせる紫陽花の花言葉には、三つの全く異なるイメージがあります。一つは「浮気」「移り気」など好ましくないもの。これは、土の成分によって色が次々と変わることから連想したのでしょう。
北は青森県・外ヶ浜町、南は熊本県・宇土市まで、全国40近くの市町村が紫陽花をシンボルの花に指定しています。しかし、これだけ違うイメージを持つ花だけに、選定にあたって紛糾したところもあります。
紫陽花が候補にあがると、委員の一人が「あれは、ゆうれん(幽霊の高松などでの方言)花言うてね、あんまり縁起がいいことありませんよ」と強硬に反対しました。そこで、陳氏は次のように反論しました。
≪そこで、白居易(白唐の詩人)が「山花一樹あり、人の名を知るなし。色は紫にして気は香る。芳麗愛すべし」という詩(七言絶句)を作ってほめた。漢字名の紫陽花は、大詩人の命名である。それなのにまだ幽霊花だとか言われているのは情けない。せめて神戸市花に推薦してあげようではないか。≫
神戸市では、阪神淡路大震災の翌年の1995年から、全国から寄せられた支援に感謝する「あじさいコンサート」が開かれており、今年で23回目を数えました=写真は今年1月の同コンサート=。プレミアムフラワーの花コラム
三つの異なるイメージを持つ花

二つ目は「一家団欒」「家族の結びつき」。寄り添って咲く様を家族にたとえたものです。
そして、三つ目は「忍耐強い愛」「乙女の愛」といったロマンチックなもの。江戸時代にドイツ人医師シーボルトが国外追放になった際、紫陽花をドイツに持ち帰り、別れ離れになった親しい女性お滝さんにちなんで「オタクサ」と名付けた――というエピソードに由来します。
市町村の花の選定で紛糾したところも

神戸市では、1970年に市制80周年と万国博開催を記念して、市民の花を選定することになりました。その選考委員会でのやりとりを、委員を務めた作家の陳舜臣氏が著書『六甲随筆』(朝日新聞社刊)に記しています。
幽霊の花か国際都市の花か

≪国際都市・神戸だからこそ、日本原産の紫陽花が望ましい。その昔、遣唐使らの衣服などについた紫陽花の種が中国・杭州あたりに根付いたが、誰も名前を知らない。=写真は奈良・矢田寺の紫陽花=≫
紫陽花の漢字名を命名したのは白居易
陳氏の発言が決め手になったのでしょう、議論の末に紫陽花が選定されました。
あじさいは咲く 哀しみをこえて

プログラムの最後に参加者全員で「あじさいを咲かそう」(作詞 阪本繁、作曲 臼井真、編曲 松下行馬)を歌います。その歌には、次のような歌詞があります。
大地が動き 炎が叫び
友を奪った あの日 あの時
あじさいは咲く 悲しみこえて
想いを抱いて 生きていくため
わたしとあなたの 胸あつい誓い
あじさいを咲かそう あじさいを根づかそう
花の色、形、エピソードのどこに着目するかで、紫陽花の花言葉は変わります。どんなイメージを抱くかは人それぞれですが、神戸では復興のシンボルの花になりました。私がこの歌を初めて聴いたのは10数年前。それ以来、紫陽花を見ると、それまでとは違った熱い思いがこみ上げてきます。
コメント
 コメントをする
コメントをする
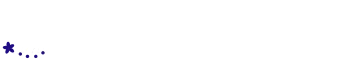
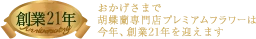
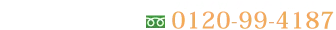
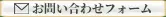
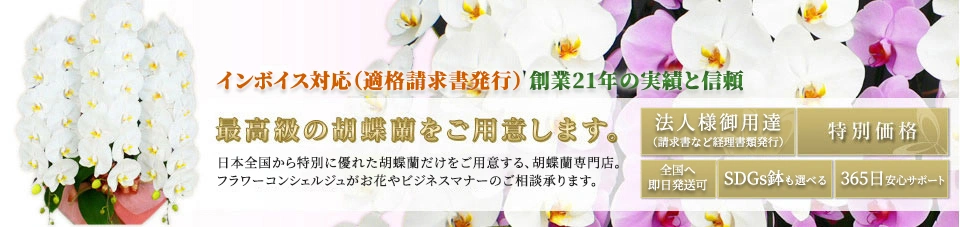
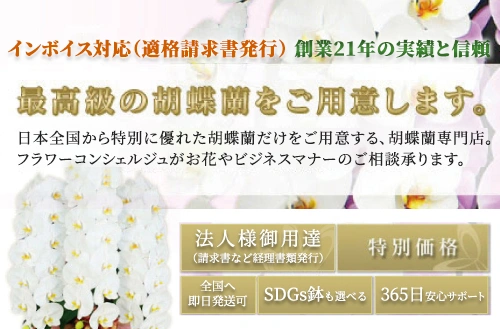
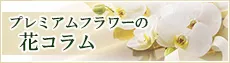
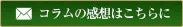
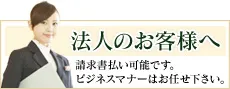

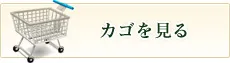
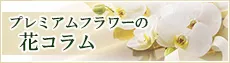
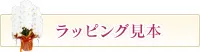


コメントはまだありません。